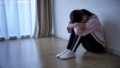会社に介護を相談する前に知っておきたいこと。上司や人事部への伝え方
なぜ会社に介護の事情を相談すべきなのか

介護と仕事の両立は一人では限界がある
介護はある日突然始まることが多く、最初は「何とか自分でやってみよう」と思いがちです。
しかし、実際には仕事との両立には限界があります。疲れやストレスが積み重なれば、仕事のパフォーマンスにも影響し、介護自体も十分にできなくなる恐れがあります。
そのため、職場に相談することは「弱さ」ではなく、むしろ責任ある行動だと私は考えています。
会社には介護を支援する制度がある
多くの企業には、介護休暇・介護休業・時短勤務といった制度が用意されています。
私がこれまで支援した方の中にも「そんな制度があるなんて知らなかった」という声が多くありました。
まずは「会社に相談することで利用できる制度がある」と知ることが、両立のスタート地点です。
職場の理解が働きやすさを左右する
介護は突発的に時間が必要になる場面が多いものです。
事情を伝えておくことで、急な早退や休暇に対して周囲の理解と協力を得やすくなります。
逆に、何も伝えないままでは「責任感がない」と誤解されてしまう危険もあります。
相談は自分のキャリアを守るため
「介護のために仕事を辞めるしかない」と思い詰める方も多いですが、実際には会社の制度や支援を使えば両立できる場合が少なくありません。
会社に相談することは、自分の生活とキャリアを守るための大切な行動なのです。
✅ チェックリスト:会社に相談するメリットを理解できていますか?
—
相談前に準備しておくべき情報(介護の状況、希望する支援)

現在の介護の状況を整理する
「誰を」「どの程度」介護しているのかを具体的にまとめましょう。
例えば「母は要介護2で週3回の通院に付き添いが必要」「父は認知症で夜間の見守りが必要」など、数字や頻度を入れて説明できるように準備すると効果的です。
会社にお願いしたい支援を明確にする
「在宅勤務を週1日導入したい」「出勤時間を30分遅らせたい」など、希望する支援を具体的に整理しておくと、相談がスムーズになります。
「ただ大変です」と伝えるより、会社が判断しやすい形になります。
就業規則や介護制度を確認する
会社によって制度の内容は異なります。
事前に就業規則や人事部の案内資料を確認しておきましょう。
「制度があると知っていたら退職せずに済んだのに」と後悔する方を、私はこれまで数多く見てきました。
家族と意見を合わせておく
介護は家族全体の問題です。
「どこまで自分が担うのか」「外部サービスを利用する部分はどこか」を家族で共有しておくと、会社への説明も一貫性が出ます。
職場と家庭で話が食い違うと、余計に混乱してしまいます。
✅ チェックリスト:介護状況と希望をA4一枚にまとめられますか?
—
上司や人事部への効果的な伝え方(事実と希望)

事実を冷静に伝える
「大変です」ではなく、
「週3回の通院付き添いが必要」「夜間は母の見守りが必要」と客観的な事実を伝えることが大切です。
数字や回数を交えることで、状況をイメージしてもらいやすくなります。
希望は具体的に示す
「とにかく助けてほしい」ではなく、
「週1日の在宅勤務をお願いしたい」「1日30分の時短勤務を希望する」と具体的な希望を伝えましょう。
その方が会社としても対応しやすいのです。
上司と人事部で伝えるポイントを使い分ける
上司には「業務上の影響と調整してほしい点」、人事部には「制度利用や手続き」について相談するのが効果的です。
役割を分けて相談することで、余計な誤解を避けられるのです。
協力姿勢を具体的に表す
職場への配慮や分担を担ってくれる同僚への労いも大切なことです。
「ご迷惑をおかけしますが、業務はこのように工夫します」と伝えることで、信頼関係が生まれます。
相談はお願いではなく、共に解決する姿勢が大切です。
✅ チェックリスト:伝える内容を“事実”と“希望”に分けて話せますか?
社内制度の活用例(フレックス、時短勤務など)

フレックスタイム制度の利用
介護と仕事を両立するためにフレックスタイム制度は非常に有効です。
例えば「午前中は病院に付き添い、午後から勤務する」といった柔軟な働き方が可能になります。
私が関わったある方は、フレックスを利用して親の通院日に合わせた働き方を取り入れ、退職を回避できました。
ただし、フレックス勤務では仕事と介護で実働時間が長くなりますので、体調管理にはご注意ください。
時短勤務や在宅勤務の導入例
介護のために勤務時間を短縮したり、在宅勤務を取り入れることで大きな負担軽減につながります。
「夕方から介護が必要なので16時で退勤する」「週2日は在宅で業務を行う」といった工夫で、仕事と介護のバランスを保てるのです。
自分自身の気持ちの切り替えもとても重要な介護の要件になってきます。
介護休暇・介護休業の活用
介護の急な対応が必要なときには介護休暇・介護休業を利用できます。
私の経験では「短期間の休暇を利用して、介護サービスを整える準備ができた」と話してくれた方もいました。
介護サービスを利用するにあたっては、細かな確認や打ち合わせや申請手続きが平日の昼間に多く発生します。
初めて経験することばかりだと思いますが制度を知っているかどうかで、選択肢が大きく変わります。
職場内の介護支援制度を確認する
会社によっては、人事部に介護相談窓口があったり、福利厚生で介護サービスを紹介してくれるところもあります。
「うちの会社には介護を支援する制度はないだろうなぁ」と思い込まず、まずは上司への確認をしてみることが大切です。
就業規則にはなくとも意外と柔軟に対応してくれる職場も多いようです。
✅ チェックリスト:自分の会社で利用できる介護制度を確認しましたか?
—
まとめ:会社を「味方」につけることで介護と仕事の両立を実現する

相談は「迷惑」ではなく「必要な準備」
会社に介護を相談することは「迷惑をかける行為」ではなく、むしろ働き続けるための準備です。
制度を使わずに無理をして倒れてしまえば、会社にとっても不利益になります。
制度を知り、事実と希望を整理する
両立を実現するためには、まず会社にある制度を正しく知ることが大切です。
そのうえで、介護の事実と自分の希望を整理し、冷静に伝えることで職場の理解が得られやすくなります。
上司・人事と協力関係を築く
上司には業務への影響を、人事には制度利用の可否を相談する。
それぞれに役割を分けて話すことで、信頼関係を保ちながら制度を利用できます。
一方的に頼るのではなく「協力して乗り越える」という姿勢を示しましょう。
会社を「味方」にする意識を持つ
介護と仕事の両立は一人では難しいですが、会社を「味方」として巻き込めば可能性が広がります。
私の経験でも、上司や同僚の協力を得られた方は、精神的にも支えられ、介護を続けやすくなっていました。
会社を頼ることは、自分と家族を守る大切な手段なのです。
✅ チェックリスト:相談を“お願い”ではなく“協力”として伝えられますか?