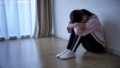導入:ヤングケアラーとは?その実態と背景
「ヤングケアラー」という言葉を耳にしたことはありますか?
ヤングケアラーとは、本来であれば大人が担うべき家族の介護や世話を日常的に行っている18歳未満の子どものことを指します。例えば、病気や障害を持つ親の身の回りの世話、きょうだいの世話、家事全般を担うケースなどが含まれます。
一概には言えませんが、彼らは「家族を支えたい」という想いから役割を担っています。しかしその背景には、社会的支援の不足や家庭の孤立など、構造的な問題が横たわっています。
私自身、地域包括支援センターで働いていた頃、介護をするお子さんと出会ったことがありました。その姿はけなげでありながらも、同時に深い孤独を感じているように思えたのです。
まずはヤングケアラーが直面している現実に目を向けることが、支援の第一歩となります。
ヤングケアラーが直面する課題(学業・就労・心のケア)
学業への影響
学校に通いながら介護を担うことは、大きな負担です。
宿題や勉強の時間が確保できない、遅刻や欠席が増える、といった課題が顕著に表れます。結果として学力の低下や進学の断念につながることも少なくありません。私が出会った中学生のヤングケアラーも、部活をあきらめて家事を優先していました。
就労への影響
高校を卒業してすぐに働く若者にとっても、家庭の介護は大きな壁になります。
シフトの調整ができずに離職してしまったり、キャリア形成が制限される場合があります。社会人になっても「ケアラーとしての役割」が影を落とすことは珍しくありません。
心のケアの不足
ヤングケアラーは「自分だけが頑張らなければいけない」と孤立感を抱えがちです。
周囲に打ち明けられず、気づかれないまま心の負担を抱え込み、不安やうつ状態に陥ることもあります。大人の介護者に比べ、相談先が見つかりにくい点も深刻です。
成長への影響
思春期は本来、友人関係や自己実現に向けて成長していく時期です。
しかし介護を担う子どもたちは、遊びや挑戦の機会を犠牲にせざるを得ない場面が多いのです。そのことが将来にわたって自己肯定感や社会参加意欲に影響を及ぼす可能性もあります。
社会や行政が進めている支援制度(相談窓口・奨学金・自治体の支援)

相談窓口の整備
文部科学省や厚生労働省は近年、ヤングケアラーの実態調査を進めています。
各自治体にも相談窓口が設置されつつあり、スクールカウンセラーや地域包括支援センターが受け皿になるケースも増えています。声をあげれば必ず誰かが応えてくれる体制が少しずつ整ってきました。
経済的支援(奨学金など)
学費や生活費の負担を軽減するために、奨学金や生活支援の制度も活用できます。
「日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金制度や自治体独自の就学支援金など、経済面での手立ては多様です。必要に応じて学校の先生や相談員に情報を尋ねてみるとよいでしょう。
自治体の取り組み
自治体によってはヤングケアラー支援条例を制定したり、相談会やピアサポートの場を設けています。
例えばある自治体では、介護サービスの利用調整を迅速に行い、子どもが介護に過度に縛られない仕組みを整えています。
情報発信と啓発活動
社会に理解を広めることも行政の大切な役割です。
学校や地域での啓発活動、パンフレット配布、SNSを活用した広報など、さまざまな手段で「ヤングケアラーが一人ではない」ことを伝える取り組みが広がっています。
学校や職場ができる配慮(柔軟な対応・相談体制)

柔軟な学習支援
学校現場では、欠席や遅刻に理解を示し、課題提出や試験の柔軟な対応が求められます。
「できていないことを責める」のではなく、「どうしたら続けられるか」を一緒に考える姿勢が大切です。
まず、当事者が「この人には、話をしてみよう」と信頼してもらえるような暖かなまなざしを向けていきましょう。
相談体制の強化
スクールソーシャルワーカーや保健室の先生が相談を受けやすい体制を整えることも有効です。
職場においても、産業カウンセラーや人事部門が理解を示すだけで、ヤングケアラー本人の安心感は大きく変わります。
そして、地域の相談窓口には電話で相談できる専門機関も整備されてきています。
周囲の理解と共感
同級生や同僚に理解が広がることで、「隠さなくてもいい」と思える環境が生まれます。
特に学校では、クラス全体で支え合う雰囲気づくりがヤングケアラーの心を支えることにつながります。
学校にはヤングケアラーを支援する制度や窓口が用意されています。
制度活用のサポート
教員や上司が制度や支援窓口を紹介し、申請の手助けをすることも実践的な支援です。
「制度は道具、使い方がカギ」ですから、まずは本人や家族がそれを知ることが第一歩になります。
支援の窓口についてのパンフレットなどで、窓口を当事者へ知らせることも一つの方法になります。
当事者の声を社会に届ける意味
「見えない存在」を可視化する
ヤングケアラーはまだ社会の中で十分に認知されていません。
テレビ番組で紹介されるヤングケアラーの姿はごくまれにしか社会の目に触れません。
当事者の声を届けることは、彼らの存在を「見えるもの」にする大切な行為です。
制度改善への影響
現場の声が行政に届くことで、制度や法律の改善が進む可能性があります。
ヤングケアラーは自分の置かれた環境を諦めながらも黙って耐えて受け止めていることが多くみられます。
私も地域包括で働いていた際、住民の声を行政に伝える役割を果たしましたが、「声が届く」ことで確実に施策は変わります。
社会の理解を深める
当事者の体験を聞くことで、多くの人がヤングケアラーの現実を理解し、共感を持つことができます。
当事者の声を聞き取ることは難しいと思われるかもしれませんが、身近な地域へ目を向けることはとても大事なことです。
「知らなかった」を「知っている」に変えることが支援の輪を広げる力となります。
次世代へのメッセージ
声を上げることは、未来のヤングケアラーへの道しるべにもなります。
辛く苦しい毎日を変える方法を知らない当事者が今日もひとりで家族を支えています。
「一人じゃない」というメッセージは、過去・現在・未来をつなぐ大切な架け橋です。
まとめ:ヤングケアラーを一人にしないために、周囲ができること

ヤングケアラーは、社会がまだ十分に光を当てていない存在です。
しかし、支援制度や相談窓口は少しずつ整いつつあります。学校や職場、そして地域社会が連携し、「あなたは一人じゃない」と伝えることが大切です。
きっと、本人の苦しい日々を分かってもらえることを待っていることでしょう。
私が介護の現場で学んだことのひとつは、「当事者の声を丁寧に聴く」こと。
それはヤングケアラーへの支援にも共通しています。まずは周囲の人が気づき、そっと寄り添うことから始めていきましょう。